骨粗鬆症治療は治るのか
骨密度の”再検査”をしたけど、去年よりも骨密度が下がっている!
骨粗鬆症が原因の骨折だと言われたけど、治るの?
骨密度の低下や、骨粗鬆症が原因の様々な骨折。これらは本当に治るのでしょうか?
医師は様々な点を考慮し、今までの生活が続けられるように治療方針を立てます。
治療効果が出る人もいらっしゃれば、病気や体質などが原因で、思うように治療効果が出ない方もいらっしゃいます。
今回の記事では、骨粗鬆症治療は治るのかについて解説していきます。
Contents
骨密度を上げる治療
骨密度を上げるための治療は、薬物療法や運動療法、食事療法が挙げられます。
それぞれの治療をどのように行っていくのか、解説していきます。
薬物療法
骨粗鬆症と診断されると、多くの場合、薬物療法が開始になります。使われる薬は、内服薬や注射など様々です。
注射は、副作用の面から、継続的に使える期間が決まっているものがあります。薬の種類により投与できる期間に違いはありますが、連続で治療できる期間は1年~2年程度です。
一定の治療期間が終了した後は、内服薬に変更される場合があります。
注射の効果も様々ですが、目的は「骨を丈夫にすること」です。
しかし、歳を重ねるとともに、体を丈夫に保っておく能力は下がりますし、ホルモンバランスがさらに崩れてしまうなどの影響により、思ったように効果が出ない場合もあります。
また、骨粗鬆症以外に病気がある場合や、ステロイドを長期間使用しなければならない場合など、骨を弱くしてしまう要素があると、さらに治療効果は出にくくなってしまうことが考えられるのです。
一方で、薬をしっかりと使用し、治療が成功している例もあります。
薬の効果の出方は、患者さんの状況や薬の使い方により様々です。
効果が出ていないようであれば、医師と相談しつつ、薬の変更などを行っていきましょう。
運動療法
歩行や筋力トレーニングなどで、骨の強度を上げることは可能といわれています。しかし、もともと運動習慣がない人や、運動自体があまり好きではない人の場合、長期間運動を続けることは難しい場合があります。
数日運動しただけでは骨は丈夫にはなりませんので、習慣となる運動が必要です。
運動が続かない場合、治療効果がうまく発揮されないことも考えられます。
研究で、運動には骨を丈夫にする作用があることがわかっています。効果をしっかりと出せるように運動を習慣化していきましょう。
食事療法
食事療法も薬物療法や運動療法と同様に、短期間で効果を出すことは難しいです。カルシウムやビタミン、タンパク質など、骨の形成に必要な栄養素をしっかりと摂っていく必要があります。
特に不足しがちなカルシウムを補うために、普段の料理に乳製品を1品追加してみたり、料理で栄養素を補足していくことが難しければ、サプリメントの利用も検討しても良いですね。
治療は長期間かかるという認識を
骨粗鬆症と言われてしまうと、「すぐにでも良くしたい」、「健康なあの時の戻りたい」と誰でも思うものです。しかし、短期間で効果が出るものではありません。
定期的に骨密度を測定し、自分が行っている治療の効果が出ているのか、治療の継続が可能なのか、医師と一緒に判断していきましょう。
薬の服用や注射が困難な場合は、医師に相談してみてください。別の治療薬を紹介してくれたり、代替え手段を提案してくれたりするかもしれません。
長期間頑張り続けることは大変ですが、一緒に治療を乗り越えていきましょう。
骨折に関して
骨粗鬆症が原因で、骨折する場合があります。骨粗鬆症で骨折する主な部位は、背骨や足の付け根、手首などです。
代表的な骨折がきちんと治るのか、解説していきます。
背骨の骨折
背骨が折れてしまった場合、程度にもよりますが、背骨の形が変わってしまう場合が多いです。中には手術により、背骨の形を元に戻す方法もありますが、多くの場合は潰れたまま背骨が固まるのを待ちます。
背骨が固まれば痛みは軽減しますが、骨の形が変わってしまうので、背中や腰は少し曲がってしまうことが勘がられます。一度背骨が曲がってしまうと、骨折前の姿勢に完全に戻すことは困難なケースが多く、後遺症として残ってしまうことが考えられるのです。
足の付け根の骨折
足の付け根は、構造上、骨折が治りづらいとされています。そのため、一度骨折をしてしまうと、人工の骨に入れ替える手術をされる方が多いです。
人工の骨にしてしまえば、手術の翌日から歩く練習が行える場合もあります。
よほど高齢でなければ、手術後も骨折前と同等の生活ができる可能性がありますが、もともと虚弱な体質の方であれば、杖や押し車などを使った生活になる可能性もあります。
手首の骨折
人は転ぶと、体を守るために反射的に手が出ます。
そのため、転倒に伴い、手首を骨折してしまう人が多いです。
手首の骨折をした場合、基本的にはギプスで固定をして、骨がくっつくまで待ちます。
骨折の程度が軽ければ、手首の動きに障害が残る可能性は低いですが、骨折の程度が重いと、手術になるケースもあり、手首の動きに硬さが残る可能性が出てくるのです。
手首に後遺症が残るかどうかは、骨折の程度や、手術後のリハビリの進み具合などによっても違ってきます。
まとめ
今回は、骨粗鬆症治療は治るのかについて解説してきました。
骨粗鬆症の治療は様々な方法があり、患者さんによって適応になる治療も様々です。
骨の状態が改善するまでには少し時間を要してしまいますが、骨を丈夫にし、骨折しにくい体にするように、目標に向かって治療を行っていきましょう。
治療を続けるのは大変かもしれませんが、医師や看護師と相談をしつつ、治療の効果を最大にできるように、一緒に頑張っていきましょう。
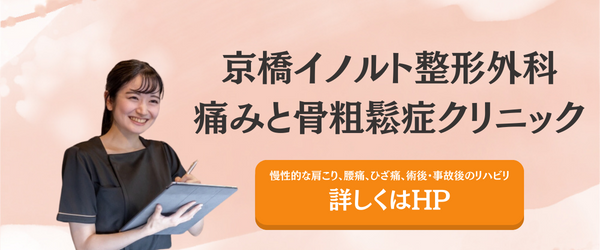
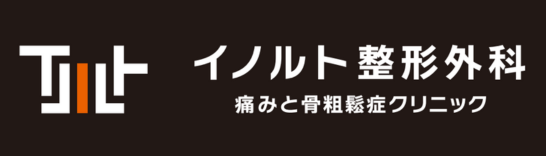

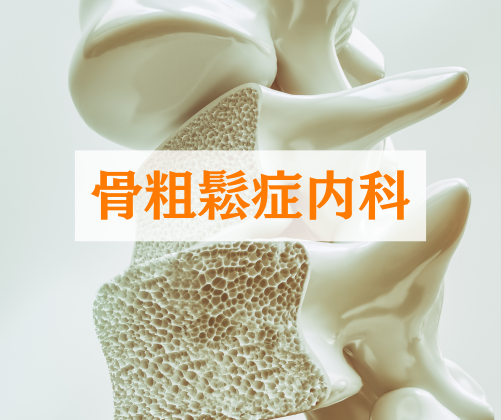

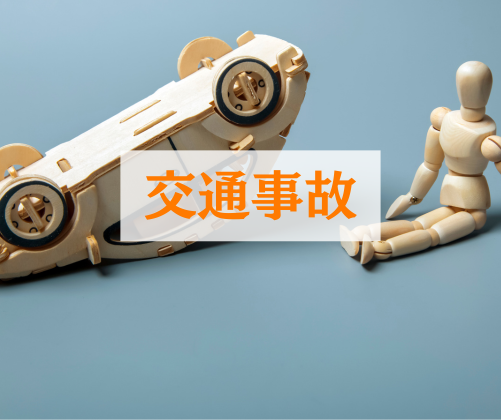
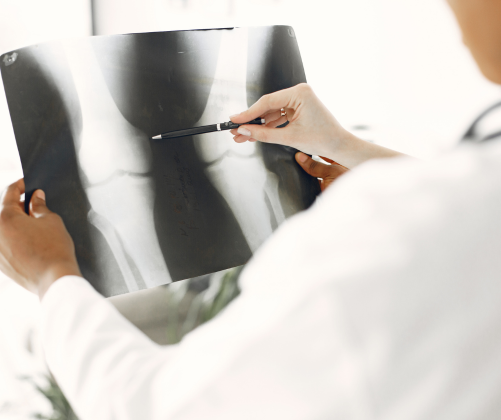







・厚生労働省e-ヘルスネット:骨粗鬆症のための運動
・日本整形外科学会:大腿骨頸部骨折
・日本整形外科学会:脊椎椎体圧迫骨折
・日本整形外科学会:橈骨遠位端骨折(コレス骨折・スミス骨折)